トップページ > 大学の技術・ノウハウ
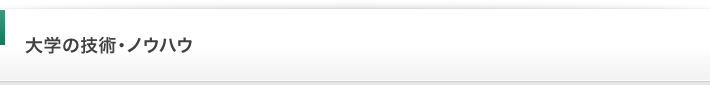
| 組織名 | 国立大学法人 電気通信大学大学院 大学院情報理工学研究科 基盤理工学専攻 牧 昌次郎 教授 |
|---|---|
| 技術分野 | ナノテクノロジー、医工連携/ライフサイエンス、環境/有機化学/無機化学 |
バイオイメージングは、細胞内の酵素などを発光物質(バイオプローブ)で光らせることで、非侵襲的かつリアルタイムに生体内現象を可視化・観察することが可能な技術として近年注目されています。特に、発光イメージングは生体深部の細胞や臓器を可視化できるため、がん治療、再生医療研究等、生命科学や医療技術開発をはじめとするライフサイエンス分野での期待は大きく、以下の技術が求められています。 1)高輝度であるこ...
| 組織名 | 国立大学法人 電気通信大学大学院 大学院情報理工学研究科 基盤理工学専攻 牧 昌次郎 教授/研究設備センター北田 昇雄特任助教 日本女子大学 理学部 化学生命科学科 森屋 亮平助教(開発当時 東京薬科大学 薬学部 嘱託助教) |
|---|---|
| 技術分野 | ナノテクノロジー、医工連携/ライフサイエンス、環境/有機化学/無機化学 |
バイオイメージングは、細胞内の酵素などを発光物質(バイオプローブ)で光らせることで、非侵襲的かつリアルタイムに生体内現象を可視化・観察することが可能な技術として近年注目されています。特に、発光イメージングは生体深部の細胞や臓器を可視化できるため、がん治療、再生医療研究等、生命科学や医療技術開発をはじめとするライフサイエンス分野での期待は大きく、以下の技術が求められています。 1)高輝度であるこ...
| 組織名 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 菊地 聖史 教授 |
|---|---|
| 技術分野 | ものづくり、医工連携/ライフサイエンス |
近年、歯科へのCAD/CAM技術の導入により、歯科技工領域を中心としてデジタル化が急速に進んでいます。一方、歯の切削は、依然として手作業で行っています。本技術は、歯の切削を自動で行う歯科治療ロボットの開発によって“Software-Defined Dentistry”を具現化することを目的としています。 歯科治療ロボットの効果として、歯の切削精度の向上とばらつきの減少が考えられます。これにより歯科修復物の適合精度が向上し、装着...
| 組織名 | 鹿児島大学 理工学域工学系 理工学研究科(工学系) 熊澤 典良 准教授 |
|---|---|
| 技術分野 | IT、センサー/デバイス |
短距離走などの陸上選手が自主トレーニングをする際、スタート練習においては号砲を発する補助者が必要であったり、また走力を客観的に評価することが難しいといった課題があり、一人では効果的な練習を行うことは困難です。鹿児島大学 熊澤教授が開発した自主トレーニング装置は、安価なウェアラブルセンサーと、設置型の赤外線通信機により構成され、センサーが号砲音を発してスタート練習ができ、また、走者の加速度を直接...
| 組織名 | 国立大学法人 電気通信大学 基盤理工学専攻 脳科学ライフサポート研究センター 牧 昌次郎 教授 |
|---|---|
| 技術分野 | 医工連携/ライフサイエンス、新エネルギー/省エネルギー、環境/有機化学/無機化学 |
金属・高分子・カーボンなどに対して白金を担持するシート状の触媒技術です。1)繰り返し利用が可能(リユース)、2)触媒使用量の低減(リデュース)、3)回収・再活性化が容易(リサイクル)、4)量産が容易、5)低価格、を実現しています。
| 組織名 | 感性 AI 株式会社(電気通信大学発ベンチャー) |
|---|---|
| 技術分野 | IT、その他、ものづくり |
「感性AIアナリティクス」は、消費者データを学習したAIが、「ネーミング」「キャッチコピー」「パッケージ」といった商品の重要な要素の感性データを瞬時に出力するイメージ分析AIツールです。新商品開発や既存商品のリニューアル時において、消費者テストや調査の代替手段として活用できるほか、調査実施前のスクリーニングにも活用できます。これにより、商品企画におけるスピードの向上や市場調査コスト軽減・業務効率...
| 組織名 | 感性 AI 株式会社(電気通信大学発ベンチャー) |
|---|---|
| 技術分野 | IT、その他、ものづくり |
「感性マテリアルプラットフォーム」は、素材がもたらす感性価値を数値化して、 客観的に提示する定量化技術により、主観的で曖昧な感性ニーズから素材の探索・開発・イノベーション創出を目指すクラウドプラットフォームです。
| 組織名 | 国士舘大学 理工学部 理工学科 佐藤公俊准教授 |
|---|---|
| 技術分野 | ものづくり |
食材の表面温度を上げずに中心温度を100℃以上に加熱することができる表面冷却赤外線加熱技術を用いて、水分が抜けてさっくりとした食感でありながら表面が白いパンを焼くことに成功しました。従来の耳なしパンとは異なる食感で、また製造時間(焼成時間)が短いという特徴があります。 本技術は、サンドイッチ用の耳なし食パン製造によるフードロス削減、省エネルギーなど食品分野における技術展開を目指しております。
| 組織名 | 東洋大学 理工学部生体医工学科/バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター 前川 透 教授 |
|---|---|
| 技術分野 | 医工連携/ライフサイエンス |
現在の医薬品開発において、薬物を最も有効で、副作用が少なく、患者に優しい製剤が求められています。そのため、薬物投与の最適化=薬物・成分を「必要とする部位」へ、「必要な量」で、「必要な時間」で送達させるためのドラッグデリバリーシステム(薬物送達システム、DDS)が、現在の薬物治療のみならず、今後発展が期待される遺伝子治療や再生医療においても不可欠な技術となっています。 本研究では、多孔構造の薬物(C...
| 組織名 | 東洋大学 理工学部生体医工学科 寺田 信幸名誉教授/秋元 俊成准教授 |
|---|---|
| 技術分野 | その他、ものづくり |
マイクロ波伝送を利用して非接触で体液量を測定する装置を開発しました。電波が水中を通過すると、電波の位相が遅れます。本技術は、この原理を応用し、測定対象物を透過する電波と透過しない電波の位相差を検出する装置です。 従来、ノイズとして扱われてきた変化を測定対象とすることで新たなセンサとして活用することで、振動などの周囲の影響を受けにくい計測技術として、自動運転中のドライバーモニタリング等、自動運転の...
![]()