トップページ > 大学の技術・ノウハウ > マツオウジから単離した高活性チロシナーゼ阻害剤の研究ときのこ抽出物ライブラリー
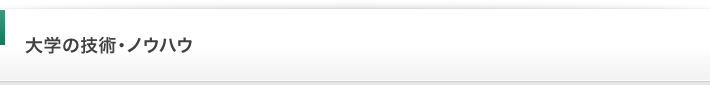
| 資料 | |
|---|---|
| 組織名 | 鳥取大学農学部 生物資源環境学科・生物資源科学講座 石原 亨 教授 |
| 技術分野 | 医工連携/ライフサイエンス , 環境/有機化学/無機化学 |
| 概要 |
きのこが特異な生理活性物質を含む事実は昔から知られています。しかし、実際には有用な生理活性物質の探索は容易ではありません。鳥取大学では、腐朽菌を中心としたきのこ抽出物ライブラリーを構築中です。その過程で、本研究室では、きのこの一種「マツオウジ」から従来にないレベルの高活性チロシナーゼ阻害剤の単離に成功しました(構造も決定済み)。本化合物に関心のある化粧品会社など、また、鳥取大学のきのこ抽出物ライブラリーを活用した新たな生理活性物質の探索・開発・実用化に興味を持つ企業等からの相談を歓迎します。 |
| お問い合わせ |
この技術・ノウハウに関するお問い合わせ |
| 詳細 | |
【簡略図】

【背景】
メラニンは毛髪の色素となるほか、皮膚中で生成してシミやそばかすの原因となる物質です。そのため、美白化粧品ではメラニンの生成をいかに抑えるかが重要な課題となっています。
メラニンは、アミノ酸の一種であるチロシンを出発物質として、L-ドーパ、ドーパキノン等を介して生合成されることが知られています。ここで、チロシンをL-ドーパに、また、L-ドーパをドーパキノンに変換する過程ではチロシナーゼという酸化酵素が働きます(下図)。

したがって、チロシナーゼの作用を阻害すればメラニンの生成を抑えることが可能であり、従来、アルブチンやヒドロキノンといったチロシナーゼ阻害剤が美白化粧品では多く使われています。
ヒドロキノンはチロシンやL-ドーパと構造が類似しており、チロシナーゼに対し、その本来の基質(チロシンやL-ドーパ)と競合的に結合し、その結果、チロシナーゼがチロシンやL-ドーパに作用するのを阻害します(拮抗阻害)。また、アルブチンはヒドロキノンの配糖体であり、同様にチロシナーゼ阻害剤として働きます。
一方、鳥取大学では「菌類きのこ遺伝資源研究センター」において多数のきのこ菌株を保有しており、その有効利用を図るためにきのこ(天然子実体、培養子実体)や菌糸体培養液等に関して、抽出物ライブラリーを構築中です。

そこで、この抽出物ライブラリーから選択したきのこ抽出物を用いてチロシナーゼ阻害活性について検討しました。下記のようにL-ドーパ含有液に対してきのこ抽出物を加えた後、チロシナーゼを添加し、反応後の色(吸光度)を観察します。チロシナーゼが有効に作用するとドーパキノン(及びドーパクロム)が生成するため、その吸収ピークにおいて吸光度を測定すればチロシナーゼの活性が測定できます。チロシナーゼが阻害されている場合は、475nmでの吸光度が低くなります。

これを多数のきのこ抽出物について行った結果、「マツオウジ」に関して、特に高いチロシナーゼ阻害活性が確認されました。

【技術内容】
本研究室でのさらなる研究の結果、マツオウジ中の有効成分(チロシナーゼ阻害物質)は下記の2物質であることが判明しています(特許出願中)。

これらの化合物のチロシナーゼ阻害活性は下図に示されるように、従来公知のヒドロキノンやアルブチンと比較してIC50価が桁違いに低い(つまり、高活性である)ことが確認されています。

なお、Lineweaver-Burkプロットの結果からは、これらの化合物の作用機序も拮抗阻害であると考えられます。
このように、本研究室が同定確認したチロシナーゼ阻害剤は、画期的と言っても過言ではない、際めて高い阻害活性を示すものであり、美白化粧品等における美白成分としての活用が期待されるものです。
【技術・ノウハウの強み(新規性、優位性、有用性) 】
本研究室も加わっている「菌類きのこ遺伝資源研究センター」では、多数のきのこ抽出物を用いた研究を行っています。その技術の優位性としては以下の点が挙げられます。
・1981~2005年までにアメリカ食品医薬局(FDA)で認可された新薬1147 品目の28%が低分子天然化合物由来で、ヒントにした医薬品も入れると52%が天然物由来であり、天然物からの医薬品探究は時代のトレンドである。
・1980年以降、天然物由来の生理活性物質の探索は放線菌から菌類にシフトしてきている。
・もっとも、きのこ(子実体)の生育には時間が掛かる上に生育条件に困難等もあり、従来、活性成分のスクリーニングに用いるのには問題があったが、「菌類きのこ遺伝資源研究センター」では既にライブラリーとして構築しているため、生育に手間を掛ける必要がない。
・菌糸体の培養により培養液中に分泌・漏出する成分についても対応している。
・抽出溶媒等の条件が明確で多様である。
・腐朽菌を中心として広汎なライブラリーを構築中である(下図)。
・効果の治験についても鳥取大学内の医学系・獣医系研究部門との連携が可能である。
・きのこの専門家のみならず、植物等を研究のバックグラウンドとする研究者との複合体であるため、深い知見を得ることができる。

※なお、菌株及び抽出物サンプル数は常に増えております。
【連携企業のイメージ】
チロシナーゼ阻害剤については、化粧品会社等との連携が可能ですが、その他、きのこ抽出物ライブラリーについては、例えば下記の企業と連携可能です。
1)製薬会社・農薬会社
2)化粧品会社等の医薬部外品メーカー
3)機能性食品・健康食品メーカー
4)鳥取県産の産品の活用を計画している企業・団体
5)上記のほか、きのこの研究者。
【技術・ノウハウの活用シーン(イメージ) 】
本技術の活用に興味がある方はお気軽にお問合せください。
【専門用語の解説】
【きのこ】
菌類の中でも、肉眼で見える程度の子実体を形成する生物及び、特にその子実体を指します。なお、菌類とは、一般にきのこ・カビ・酵母と呼ばれる生物の総称であり、菌界(学名:Regnum Fungi)に属する生物を指します。細菌と特に区別するため真菌と呼ぶこともあります。細菌が原核生物なのに対し真菌は真核生物であり、両者は全く異なります。真菌には子嚢菌門と担子菌門等があり、担子菌門は文字通り子実体(いわゆる「きのこ」)を担う菌類です。
【腐朽菌】
木材に含まれる難分解性のリグニン、セルロース、ヘミセルロースを分解する能力を有する菌類。シイタケ、ナメコ、エノキタケ、ヒラタケ、マイタケ、タモギタケ(以上は白色腐朽菌)とサルノコシカケ、マツオウジ(以上は褐色腐朽菌)があります。腐朽菌に対し菌根を作って植物と共生する菌類は菌根菌と呼ばれ、こちらの液体培養は困難です。マツタケ等は菌根菌です。
【マツオウジ】
マツ科の枯れ木や倒木等から生える腐朽菌の一種。傘の直径は5~20cm程度で食用になるが、苦味があり、生食ではなく茹でこぼして食べる。

メールフォームのご利用は、以下の項目にご記入のうえ「送信する」ボタンを押してください。
担当者より折り返しご連絡いたします。
個人情報の取り扱いについては、こちらをご覧ください。
![]()